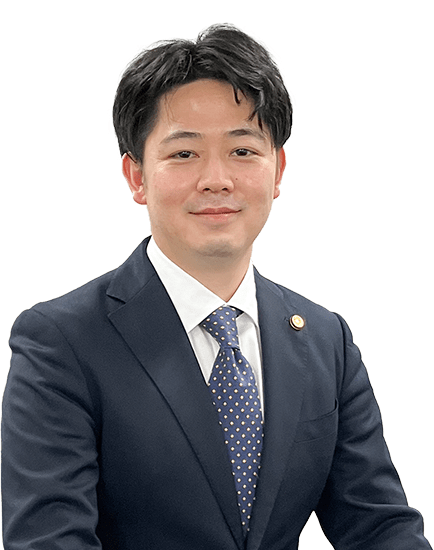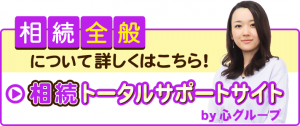- トップ
- ブログ
ブログ
特別受益
東京も徐々に涼しくなってきました。
寒暖差が大きく、体調管理には気を付けたいですね。
さて、相続のご相談を受けていると、「特別受益」についてのご質問をよく受けます。今日は特別受益について解説します。
1 特別受益とは
相続人の一人が、被相続人から遺贈を受けた場合や被相続人の生前に贈与を受けていた場合、相続に際して、この相続人が他の相続人と同じ相続分を受けるとすれば、結果としてこの相続人だけが遺産を多く貰えることとなってしまい、不公平な結果となります。
そこで、民法は、相続人のうち一人が、被相続人の生前に婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生活の資本として贈与を受けていた場合(これを「特別受益」といいます。)には、相続分の前渡しがあったとみて、相続分の計算時に特別受益を相続財産に加算して計算することとしています(民法903条1項)。
2 特別受益があった場合の計算
特別受益がある場合に相続分の計算時に特別受益を相続財産に加算して計算すると書きましたが、このことを「特別受益の持ち戻し」といいます。
例えば、Aの相続が発生し、Aの相続人が妻のBと、子のCおよびDであるとします。Aの遺産は1000万円であったのですが、Aは200万円について子のCに生前贈与していたとします。
その場合の各相続人の具体的相続分については、以下の手順で計算することとなります。
①遺産の1000万円に生前贈与の200万円を合算し、1200万円を遺産とします。
②各相続人の法定相続分は、Bが2分の1、Cおよびが4分の1ずつですので、それぞれの法定相続に従った取得分は以下の通りとなります。
A:600万円(1200万円×2分の1)
B:300万円(1200万円×4分の1)
C:300万円(1200万円×4分の1)
③Cは生前に200万円を既にAから貰っているので その分を考慮して、最終的なA、B、Cの取り分は以下の通りとなります。
A:600万円
B:300万円
C:100万円(300万円-200万円)
3 特別受益がある場合の例
特別受益として持ち戻しが争われる例としては、遺贈や生前贈与のほかに、被相続人の土地を相続人が無償で使用していた場合や特定の相続人が高額な被相続人の死亡保険金を受け取るようなケースもあり得ます。
特別受益の有無の認定は、過去の裁判例・判例を踏まえて、事案ごとの事情を分析する必要がありますので、特別受益の有無については弁護士に相談することをお勧めします。
遺言執行者
先日まで猛暑日が続いていましたが、ようやく少しずつ涼しくなってきましたね。
前回まで遺言関係の記事を書いていましたので、今回も遺言シリーズとして「遺言執行者」について書いていきたいと思います。
1 遺言執行者とは
そもそも、遺言執行者とは何でしょうか。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために遺言執行の手続を行う人のことを言います。遺言執行者は遺言で指定することできるのですが、誰でもなれるわけではありません。
民法上では、未成年者と破産者も遺言執行者になることはできないとされています(民法1009条)。
遺言執行者は遺言者の財産を管理する権利・義務を有しますので、遺言執行者となる人には、完全な行為能力(単独で確定的に有効な法律行為をする能力をいいます)が求められていますが、その以外には特に明文上の制限はありません。遺言執行者には、法人もなることができますし、相続人や受遺者がなることもできます。
2 家庭裁判所による選任
また、遺言書に遺言執行者が定められていない場合や遺言執行者が定められていたものの遺言執行者が死亡した場合等には、利害関係人が請求することにより、相続開始時の家庭裁判所が遺言執行者を定めることとなります。
遺言書に遺言執行の定めをする場合、遺言執行者を誰とするべきか、遺言執行者の権限として何を記載するべきか専門的な知識が必要となってきます。
遺言を作成する場合や遺言執行者の選任をお考えになっている場合には、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
検認手続について
ここ数日、相変わらず暑いですね。
通勤しているだけで汗びっしょりになります。
皆様もご体調には気を付けてください。
さて、前回遺言書の作成についての記事を書きましたが、今回は自筆の遺言書が見つかった場合の手続について解説します。
あまり、聞きなじみはないかと思いますが、自筆証書が見つかった場合「検認」という手続を行わないといけません。今日は検認手続について解説します。
1 検認とは
ご相続発生後に遺言書が発見された場合、家庭裁判所に対して、「検認」という手続をとる必要があります。「検認」とは、相続人に対して遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
2 検認の手続
遺言を発見した場合、発見者は家庭裁判所へ検認の申し立てを行うことになります。検認の申し立てがあると、家庭裁判所から相続人に対して検認を行う期日の通知がなされ、検認の日が決まります。検認期日当日は、相続人等の立ち会いの下、裁判官が遺言書を開封します。検認では、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の状態や遺言書の内容が確認されます。検認が終わった後、家庭裁判所に対して申請すると検認済証明書という証明書が、発行されます。遺言の執行を行う場合には、この検認済証明書が必要となりますので、執行者となられる方は申請しておきましょう。
弊所東京事務所でも「自筆証書遺言が見つかったが、今後どのような手続をすればよいのか」というご相談を受けることがあります。自筆証書遺言の場合、上記の検認手続をとらないといけませんので、注意しましょう。
自筆証書遺言の場合、検認手続のほかにも遺言書の有効性等、法的な知識が必要になることがあります。
遺言書が見つかった場合には、弁護士に相談してみてください。
遺言作成の際に必要になるもの
私は、東京事務所や千葉事務所でご相談を受けることが多いですが、遺言についてのご相談を受けることも多いです。
多く受けるご質問としては、「遺言を作成したいけれど、作成の仕方が分からない。方法や手続の仕方を教えて欲しい」というものです。そこで、遺言の作成について解説します。
1 遺言書の種類
まず、遺言にはどのような種類があるのでしょうか。
一般的によく利用される遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言とは、遺言者が自筆で書いた遺言書のことを指します。自筆証書遺言が有効に成立するためには、①遺言の内容となる全文、②日付、③氏名の全てを自筆し、さらに④押印することが求められます。自筆証書遺言は、公正証書遺言と比較して手軽に作成できる反面、
無くしてしまったり、改ざんされてしまうリスクもあり、相続発生後に遺言の有効性が争われるケースも少なくありません。
これに対して、公正証書遺言とは、公証役場の関与の下、遺言者が遺言を作成するものです。公正証書遺言の場合、遺言書の作成にあたっては、公証人と証人2名が関与します。公証役場において、遺言者が公証人に対して遺言の内容を伝え、公証人がその内容を筆記したうえで、遺言者と証人にその内容を読み聞かせ、又は閲覧させます。公証役場で作成するため、自筆証書遺言と比較して作成の手続が煩雑ですが、遺言の有効性等で争いになるリスクを低くすることができます。
2 公正証書遺言作成に必要な資料
公正証書遺言を作成する場合、遺言書案のほかに必要な資料を公証役場に提出する必要があります。
まず、①遺産の内容となる預貯金の通帳の写しや不動産の謄本、固定資産税評価証明書の写しが必要となります。②また、遺言者と相続人との関係を把握するため、被相続人と相続人の戸籍謄本の写しも必要となります。
遺贈をする場合には、受贈者の住民票の写しも必要となります。③さらに、公正証書遺言には実印で捺印することになりますので、公正証書遺言作成当日は実印を持参する必要があるほか、当該実印の印鑑証明書も用意する必要があります。この印鑑証明書は、遺言作成日から遡って3カ月以内という有効期限があるので、注意が必要です。
公正証書遺言を作成する場合、上記のような書類が必要となりますし、作成の段取りもやや煩雑となります。
また、公正証書遺言の場合も、遺言書の記載をどのようにするべきか法的な検討が必要になります。公正証書遺言を作成される場合には、弁護士等の専門家に一度相談することをお勧めします。
相続放棄
5月に入ってから、東京は夏日のような日が続いてますね。
先日、スーパーでスイカが売られているのを見て、びっくりしました。もはや夏ですね、、、。
さて、最近相続放棄申請業務を承ることがあります。
今日は相続放棄について、解説いたします。
1 相続放棄とは
相続放棄とは、相続開始後に相続権を放棄することをいいます。相続放棄は、遺産の積極財産と消極財産のいずれも相続することを否定することになります。例えば、遺産のうち積極財産よりも消極財産のほうが多く、遺産を承継することで損害を被るようなことが確実であるような場合には、相続放棄をすることが有用です。
2 相続放棄の期間
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所への申述によってなされます(民法第938条)が、この相続放棄の申述は、相続開始があったことを知った時から3カ月以内にしなければなりません(民法第915条第1項)。もっとも、この期間を経過した場合でも、相続放棄期間の伸長を家庭裁判所に対して申し立て、家庭裁判所がこれを認めた場合には、伸長された期間が経過するまでは相続放棄をすることができます。相続放棄の申述は、相続人が行うことができます。ただし、相続人が未成年者又は成年被後見人である場合には、当該法定代理人が相続人を代理して申述することになります。また、相続人である未成年者と法定代理人の利害が対立するような場合には、当該未成年者に対して特別代理人を選任することが必要となります。
3 相続放棄のメリット
相続放棄のメリットとしては、被相続人の負債を承継しなくても良いことにあります。相続放棄を行うと相続放棄をした人は初めから相続人ではなかったものとみなされます(民法第939条)。そのため、被相続人に借金があったとしても、相続放棄をすれば借金を承継しなくても良いことになります。また、被相続人が不動産を所有しており、その不動産の管理に費用が掛かってしまう場合も、相続放棄をすればその不動産を承継しなくて良いことになります。ただし、相続放棄をした人が、相続財産を占有していた場合には、相続財産管理人に引継ぐまでは一定程度の保存義務を負担することになっています(民法第940条第1項)。
4 相続放棄のデメリット
相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産もともに相続することを否定するものであるので、相続放棄をしてしまうとプラスの財産を承継することができません。
また、相続税との関係では、相続放棄をした人は、生命保険金や死亡退職金についての非課税枠(500万円×法定相続人の人数)の適用を受けることができなくなります。また、相続放棄をした人は、債務控除や数次相続控除も受けることができなくなりますので、注意が必要です。
相続放棄には、それぞれメリット・デメリットがありますので、相続放棄を検討される場合には弁護士にご相談されることをお勧めします。
遺産分割協議書作成のポイント
徐々に暖かくなってきましたね。
桜もすっかり散ってしまって、夏に向かって徐々に季節が移っているなぁと感じています。
さて、最近は、弁護士に遺産分割協議書の作成を依頼される方が多くいらっしゃいます。今回は、遺産分割協議の作成にあたってのポイントを纏めてみます。
1 相続人全員の合意が必要
遺産分割協議書を作成するにあたり、誰が署名・捺印しなくてはいけないのでしょうか。
遺産分割協議は、相続人全員の合意があることが必要です。相続人の一部が反対していたり、相続人の一部が欠けており、全員の合意が取れていない場合、相続人の一部の合意が確認できない遺産分割協議書は無効となりますので注意が必要です。
2 遺産分割協議書の記載
次に、遺産分割協議書には、遺産となる財産を記載しますが、どのような書き方をすればいいのでしょうか。
預金等の金融資産を記載する場合、遺産を特定するために、金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号を正確に記載する必要があります。また、不動産を記載する場合も登記簿記載に記載されている事項を正確に記載しなければなりません。
不動産の場合には、登記簿謄本の記載に則って、土地でしたら、所在、地番、地目、地積を記載します。建物でしたら、所在、家屋番号、種類、構造、床面積を記載することになります。
3 実印と印鑑証明書が必要
遺産分割協議書の押印は実印で行う必要があります。また、実印で押したことを証明するために印鑑証明書も必要となります。遺産分割協議書内容に即して預金等の遺産を分配する場合、各金融機関に預金の解約等の手続が必要となりますが、遺産分割協議書に実印の押印が確認できない場合、各金融機関で手続を受け付けて貰えないので、この点は注意が必要です。
また、印鑑証明書の有効期限ですが、法務局で不動産の名義変更手続を行うだけなら、住所や氏名の記載が一致していれば、古いものでも手続を行うことができます。一方で、金融機関や証券会社との関係では、有効期間が設定されていることがほとんどです。有効期間は、多くの場合は6か月ですが、短いところでは3か月とされています。
不動産査定の見方のポイント
弁護士として相続案件に関わっていますと不動産の評価が争点となることも多いです。その場合には、不動産会社に査定を依頼することが多いですが、この査定を依頼するときや査定書を見るときに注意すべきポイントがあります。
第1に、対象不動産の売却先として誰を想定しているのかによって価格に違いが生じます。例えば、土地付きの戸建の査定をするとした場合、不動産会社に売却する場合と一般個人に売却する場合とが想定されます。
不動産会社の場合、建物を壊すなりリフォームするなりして、最終的には販売して利益を得ることが目的であることが多いですので、不動産会社が最終的に得られる利益も考慮して、仕入をする価格 (売主側から見ると、売却価格)が決まります。
一方で、一般個人に売却する場合には、転売や再販することは通常は考えられず、建物を壊して新しく自分用に建物を建てるか、建物は壊さずに中古物件として購入するケースが多いです。いずれにせよ、不動産会社とは異なり、自分で使うことが想定されます。
そうすると、自分で気に入った物件であれば、予算が許す限り手に入れたいと思いますから、(一般的には事業利益を考慮して価格を決める)不動産会社と比較すると高く価格が付くケースが多いです。
第2に想定する売却条件も重要です。上記と同様に土地付きの戸建で考えると、建物付き(現況有姿)で売却するのか、更地にしてから売却するかによって、買主が建物の解体費を支払わなくてよいかどうかに違いが生じますので、当然価格も異なってきます。また、契約不適合責任を免責するのか、売却前に確定測量をするべきか、隣地から越境物があった場合に解消するべきか等の条件の有無によっても価格は左右されます。
なお、売却先が不動産会社の場合、上記条件面での交渉は柔軟に対応してくれるケースがあります(例えば、契約不適合責任は免責にしてもられる等)。一方で、売却先が一般個人の場合には、不動産会社のような不動産のプロではないので、不動産会社のような条件面での交渉は難しいことが多いです。
第3にスケジュール感も重要です。個人に売却する際には、購入される個人の方もじっくり検討されたいことが多いですので、お時間がかかることがあります。一方で、不動産会社に売却する場合には、不動産会社は不動産購入のプロですので、比較的早くに不動産取引の段取りが進むことが多いです。もっとも、先に挙げた売却条件によっては、どうしてもスケジュールに影響が出てくることもあります(例えば、確定測量が必要な場合には、確定測量が完了するまで決済できないこともあります)ので、売却条件はこの点でも重要になります。
東京では規模の大きい不動産も多いですので、不動産の評価は特に重要になってきます。そのため、不動産が関わる案件の場合、不動産分野に精通した弁護士に依頼することが問題解決の近道になります。
マンションの専有部分
マンションの専有部分、共用部分という言葉を何気なく使うことがありますが、法律上、専有部分や共用部分とは何を指すのでしょうか。数回に分けて解説します。
1 専有部分
そもそも専有部分とは何でしょうか。区分所有法を確認すると「区分所有権の目的となる建物部分」とされています。
それでは、「区分所有権の目的となる建物部分」とは何を指すのでしょうか。
これも区分所有法に定めがあり、「一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができる」部分のとされています。
一般的に①構造上の独立性と②利用上の独立性という2つの要素がポイントとされています。
2 構造上の独立性
構造上の独立性とは、壁、床、天井等によって物理的に他の部分と区画されていることを指します。ただし、周囲が完全に壁等で区画されていることまでは必要とされていません。あくまでも独立の範囲が明確であればよく、シャッターでのみ仕切られているような場合でも構造上の独立性はあるとされています。
3 利用上の独立性
利用上の独立性とは、独立して建物の用途(住居、店舗、事務所、倉庫等)として利用できることを指します。利用上の独立性があるというためには、独立した出入口が存在していることが必要とされています。
例えば、他の専有部分を通らなければ外部に出られない場合には、利用上の独立性が認められないことになります。
区分所有法は、各定義が一見してイメージしづらいため、一つ一つ具体的な例をイメージしながら定義を確認する必要があります。近年、住宅市場が好調なこともあり東京でもマンションが建てられていますが、マンションの維持・管理をめぐって法律トラブルが生じることもあります。マンション関係の法律トラブルの場合、民法や区分所有法のほか、建築基準法や都市計画法等の他の法分野に横断した知識が求められることがあります。マンション関係のトラブルが生じた際には、法律の専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。
次回は、共用部分について纏めたいと思います。
祭祀財産の承継
相続のご相談を受ける中で、「お墓の管理するのは誰か」について相続人間で揉めているケースがあります。今日はお墓の管理について、法律上はどのように規律されているのか解説します。
1 民法上、「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、祖先の祭祀の主宰者に帰属する」とされています。
ここでの「系譜」とは、家系図などを指します。また、「祭具」とは、位牌や仏壇などが当たります。「墳墓」とは墓石や墓碑のことを指します。
そして、これら系譜、祭具、墳墓(これらを総称して「祭祀財産」といいます。「祭祀財産」の所有権は「祭祀の主宰者に帰属する」とされていますので、祭祀財産は遺産分割の対象となりません。つまり、例えば、お墓や位牌は遺産分割の対象にはならず、「祭祀の主宰者」のものとされているのです。
2 では、「祭祀の主宰者」とは誰になるのでしょうか。民法では、第1に被相続人の指定により、第2に慣習により、第3に家庭裁判所の審判によって定めるとされています。
3 このように民法上、祭祀財産は遺産に含まれず、相続による承継とは別の規律をしています。ただし、実務上は、相続人全員で争いがない場合には、遺産分割調停の中で祭祀承継者を指定して、祭祀財産を取得させることも可能とされています。
祭祀財産の承継は、少し特殊な規律がされていますので注意が必要です。お墓の管理等についても相続トラブルが生じた場合には、弁護士に相談してみることをお勧めします。
遺留分減殺請求と寄与分との関係
最近は気温が若干下がってきまして、少しずつ秋めいてきましたね。
今日は寄与分と遺留分減殺請求との関係について書いていこうと思います。
1 遺留分を侵害する寄与分
寄与分とは、相続人が生前の被相続人に対して特別な貢献した場合に、相続人の具体的相続分を増やす制度のことをいいます。この寄与分と遺留分減殺請求との関係について、実は民法で明文の規定はありません。
それでは、遺留分減請求権と寄与分との関係はどのように規律されるのでしょうか。
まず、寄与分を定める際に、遺留分を侵害するような寄与分を定めてはいいのでしょうか。民法上は、寄与分の額について上限の定めがないため、他の相続人の遺留分を侵害するような寄与分の定めをすることも可能です。ただし、裁判例(東京高裁平成3年12月24日)では、寄与分を定めるにあたっては、他の相続人の遺留分を侵害する結果となるかどうかについて考慮しなければならないと指摘しており、寄与分を定めるにあたっても遺留分に対して配慮が必要であるとしています。
2 遺留分減殺請求に対する寄与分の主張
次に、遺留分減殺請求に対する寄与分の主張はできるのでしょうか。
結論としては、することはできません。民法上、寄与分を理由に遺留分減殺請求を拒否する旨の定めはなく、遺留分減殺請求に対して寄与分を主張することに法的な根拠はないことになります。
3 寄与分に対する遺留分減殺請求権
遺留分減殺請求は、受遺者又は受贈者に対して行われる、すなわち、遺贈や贈与に対して行われるものとされています。寄与分は、具体的な相続分を修正するものではありますが、それは遺贈や贈与ではありませんので、遺留分減殺請求の対象外ということになります。