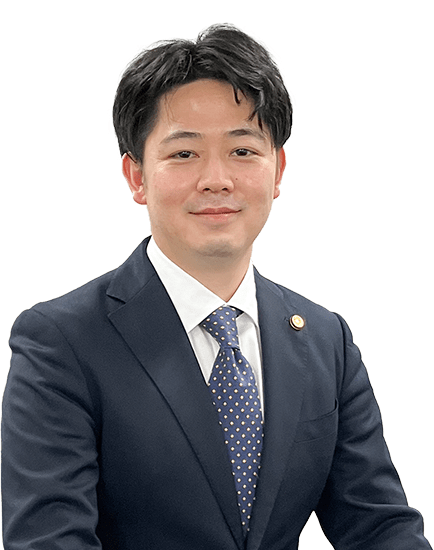皆さん、こんにちは。
東京では、相変わらず暑い日が続いています。
熱中症にならないように、適度な水分補給を心がけましょうね。
さて、今回は契約
・・・(続きはこちら)
皆さん、こんにちは。
東京では、相変わらず暑い日が続いています。
熱中症にならないように、適度な水分補給を心がけましょうね。
さて、今回は契約不適合責任のお話です。
不動産売買をしていますと、契約不適合責任というワードが良く出てきます。
弁護士業務でも契約不適合責任に関するご相談はよくあります。
契約不適合責任とは、売買契約や請負契約において、引き渡された物が契約内容と合ってない(不適合)である場合に、売主や請負人が負うべき責任のことをいいます。
昔は、「瑕疵担保責任」と言われていました。
契約不適合責任が認められますと、買主や発注者は、解除や損害賠償、不適合部分の修繕や代金の減額を請求することが出来ることになります。
例えば、不動産の売買で建物に不具合がないとして売買したのに、購入後に建物に漏水部分が判明した場合に、買主は売主に対して修繕の請求や損害賠償を請求する音が出来ることになります。
契約不適合責任が問題になる場合、まず「そもそも契約当事者が契約で、どういう性質のどういう物を契約の対象としていたのか」確定する必要があります。
この際に、不動産売買の場合に参照するべき資料としては、売買契約書や重要事項説明書が挙げられます。また、設備表や告知事項書がある場合には、それらの内容も確認することになります。また、当事者間でのやり取り(メール)も参考になります。
上記資料から、買主の購入目的や売買当事者の目的物に関する認識を確定していき、そもそも契約不適合が生じていたのかを判断していくことになります。
そのため、売買契約書や重要事項説明書はもちろんのこと、設備表や告知事項書についても、しっかり内容を確認したうえで記入しましょう。