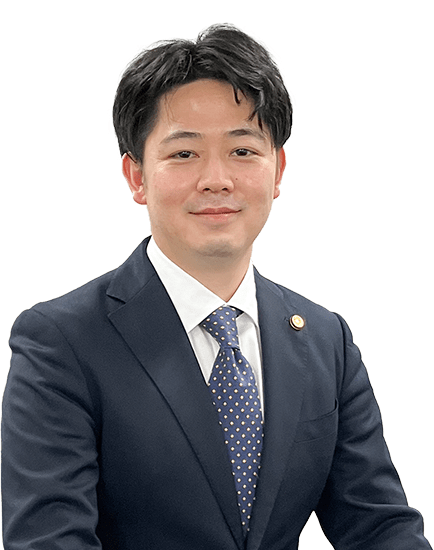皆さん、こんにちは。
今週は、東京の気温もだいぶ低くなり、本格的に秋めいてきました。
ただ、まだ日中は暑くなる日もあるので、なかなか衣替えのタイミン
・・・(続きはこちら)
皆さん、こんにちは。
今週は、東京の気温もだいぶ低くなり、本格的に秋めいてきました。
ただ、まだ日中は暑くなる日もあるので、なかなか衣替えのタイミングは難しいですね。
小さい頃は、地球温暖化と聞いても、あまり深刻なイメージを持っていませんでしたが、
ここ最近の気温の急激な変化を体感しますと、地球温暖化の危険性を身に沁みますね、、、。
さて、前回は相続放棄についての記事を書きました。
最近、弁護士業務の中で相続放棄のご相談も多いので、今回も相続放棄の話題にします。
前回、相続放棄は、原則として相続開始を知った時から3カ月以内(これを「熟慮期間」と言います)にしなければならないことを書きました。
ただ、どうしても遺産や債務の調査に時間がかかり、3カ月以内に調査が完了しない場合も有り得ます。そのような場合、熟慮期間中に家庭裁判所に期間伸長の申立てを行い、家庭裁判所から審判を得られれば、熟慮期間を伸長することができるます民法915条第1項)。
伸長の期間や回数については特に制限はなく、家庭裁判所が申立ての都度、裁量によって期間を決するとされています。
そのため、財産調査が熟慮期間内に間に合わないには、早めに熟慮期間の延長の申し立てを行っておきましょう。
ただ、注意をしなければならないのは、戸籍の収集が間に合わないことを理由として、熟慮期間の延長は認められません。そのため、戸籍の収集が間に合わない場合には、熟慮期間内に相続放棄の申述のみ先に行い、戸籍は後から追完することになります。
相続放棄もいろいろと落とし穴がありますので、相続放棄をご検討される方は、一度専門家に相談されてみたほうが良いかと思います。